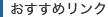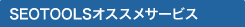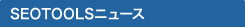10月9日から10月15日まで『国際文通週間』 「パーカー」創業者の曾孫ジェフリー・パーカー氏&放送作家・小山薫堂氏&「銀座・伊東屋」代表取締役社長・伊藤明氏が語る「忘れられない手書きのエピソード」
[16/10/06]
提供元:PRTIMES
提供元:PRTIMES
10月9日から10月15日までの1週間は、世界的に『国際文通週間』と定められています。これは、1957(昭和32)年にカナダのオタワで開催された第14回万国郵便大会議において、世界の人々が文通によって文化の交流に努め、世界平和に貢献しようという趣旨で設定されたキャンペーンです。手紙を書いて親交を深め、お互いを理解し合い、平和な世界を築こうという運動であり、今年で決議からちょうど60年目にあたります。
ニューウェル・ラバーメイド・ジャパン株式会社(住所:千代田区神田錦町1丁目1番地、代表取締役社長:松尾 昌典)が展開する、クラフトマンシップとデザイン革新のリーダーである高級筆記具ブランド「パーカー」が主催となり、8月31日に東京・銀座にある文房具専門店「伊東屋」でトークイベントが開催されました。そこでは、特別に来日した「パーカー」創業者の曾孫にあたるジェフリー・パーカー氏と、「パーカー」のブランドアンバサダーである放送作家の小山薫堂氏、そして会場となった「伊東屋」の代表取締役社長である伊藤明氏の3人が登壇し、それぞれが「手書き」にまつわるエピソードを披露しました。
■手書きには、そのときの感情が表れる
[画像1: http://prtimes.jp/i/19925/11/resize/d19925-11-419991-2.jpg ]
まず、放送作家という、モノを書くことを仕事にしている小山薫堂氏は、「昔はテレビの仕事は、ずっと手書きでした」と述懐。通称・テレ原と呼ばれたテレビ用の原稿用紙があり、1時間のバラエティー番組でだいたい60枚から70枚ほどを書き上げ、終わるころには洋服の袖口が真っ黒になっていたとそうです。その後、ワープロ、コンピューター、さらには小さなパソコンと化した携帯電話が登場し、「書く」という作業は飛躍的に効率化されて、楽になってはいますが、小山氏は逆に、今だからこそ「手書き」の機会が増えていると明かしました。それは「手で書いているほうが、勢いがあるんです」とのこと。頭の中にひらめいたアイディアをデジタル機器で記録するよりも、その一瞬の思いをバーっと手で書いたほうが、筆圧が強くなったり、字が荒くなったりはするが、そのほうが「勢い」が感じられ、さらにアイディアが広がっていくのだそうです。自身の日記は今も手書きだという小山氏。「手書き」だと、悲しいときは悲しい字に、うれしいときはうれしい字に、そして怒っているときは乱れたりするが、感情が字として表れることこそが「手書き」の魅力だと語りました。小山氏は旅をするとき、必ずトラベルノートを持っていくとも語ります。電車や飛行機の移動中に、いま抱えている仕事や悩み、そのときの心情を吐露するように手書きで日常を綴っており、それを後々になって読み直すことが面白いと言います。「旅に出たときに、自分のことを引いた目で改めて見るという習慣が、僕のストレス解消にもなっているんです」と、小山氏。その際は「万年筆で書いたほうが、後で読み返したときにカッコよく見えるんです。「パーカー」の「ソネット」は比較的、細い字で書けて、字もにじまず、小さなトラベルノートに書きやすいんです」。
■手書きは尊重されるべき個人的なコミュニケーションである
[画像2: http://prtimes.jp/i/19925/11/resize/d19925-11-315744-1.jpg ]
1888年、当時25歳だったジョージ・パーカー氏によって創業された「パーカー」は、エリザベス女王やチャールズ皇太子が愛用してきた英国王室御用達のブランドです。最初は小さな会社でしたが、非常に賢明で聡明な若き創業者によって、現在は世界的に認知された非常に大きなブランドに成長しました。創業者の曾孫にあたるジェフリー・パーカー氏は、手書きという「ハンドライティング」はパーソナルなコミュニケーションであり、今や当たり前となったデジタルとは両極端に位置するアナログな行為ではありますが、非常に重要な個人的経験として尊重すべきキーワードだと位置づけています。そもそもパーカー氏の家族は書くということが好きで、祖父のケネス・パーカー氏が1928年から1938年までつけていた日記が残されています。そこには、ケネス氏が当時、興味を持っていたこと、困難で難しいと感じていたことなどが示唆に富む形で書き記されており、それを読んだジェフリー氏は「非常にエモーショナルで、祖父の感情が手にとるように伝わってきて、そこから多くのことを学ぶことができました」と明かしました。当時は世界的な大恐慌の時代。祖父の悩み、立ちはだかる困難、しかし、それに立ち向かう思考が記され、その手書きの日記はジェフリー氏にとって、何ものにも勝る貴重な宝物になっているそうです。
■書いた記憶のないノートに自分の字が書かれていた
[画像3: http://prtimes.jp/i/19925/11/resize/d19925-11-770942-0.jpg ]
トークショーの会場となった「伊東屋」も1904年に創業した老舗の文房具専門店。今年で112年になる「伊東屋」の店頭では、販売する商品が時代によって変化し、進化していますが、常に新しく、しかし変わらない魅力を備えているのは万年筆だと伊藤明氏は言います。年代モノといわれる「パーカー」の万年筆は、当時は最新式のインクの入れ方をしており、一見レトロに見えるボディも美しく、そこにテクノロジーを感じると語ります。伊藤氏は「今のデジタルなテクノロジーは、いつか時代の流れで古くなることもありますが、「パーカー」の万年筆は決して古くならず、そういうモノが僕は好き」と、目を細めました。そんな伊藤氏がずっと忘れられない「手書き」にまつわる思い出は、氏が12歳のときに亡くなった父が書き残していたというノート。伊藤氏が新しい店舗を出店するとき、どうしたらいいか悩んでいました。「そんなとき、ふと、会社にある机の引き出しを開けたら、見たことのないノートが出てきたんです。そこの書かれている字を見て、まずはビックリしました。僕の書く字にそっくりなんです」。しかし、伊藤氏にこのノートで何かを書いたという記憶はありません。さらに、小学生で父親を亡くした伊藤氏は、父親の筆跡に関する記憶もありませんでした。「でもノートには、僕と同じ字で、まさに僕が悩んでいることがそのまま書いてあったんです。しかも、その悩みに対しての“答え”も書いてありました」。つまり、このノートは伊藤氏の父親が書いたものだったのです。「それを読んで、親子で書く字というのがこんなにも似ているんだということにまずは驚き、さらに同じことに悩んでいたということを知ったとき、まるで誰かに仕掛けられたドッキリかと思うほどでした」と笑いました。
■アメリカのホームレスが書いた1枚の紙切れ
さらに小山氏が披露する「手書き」に関する体験で記憶に残っているというのは、9年前のこと。滝田洋二郎が監督を務め、第81回アカデミー賞外国語映画賞、および第32回日本アカデミー賞最優秀作品賞などを受賞した2008年公開の映画『おくりびと』の脚本を担当したのが小山氏でした。アメリカのカリフォルニア州サンフランシスコ・ベイエリアの北部に位置するナパバレーで、映画の脚本を書いていた小山氏。第1稿をようやく書き終えた小山氏は、その解放感から日本食の『うどん』が恋しくなり、そのためにレンタカーを借りて、サンフランシスコにある有名な日本料理店に向かうことにしました。ただし、すぐに脚本の推敲に取りかからなくてはいけなかったこともあり、お金はそれほど持たず、とりあえず20ドル紙幣のみをポケットにねじ込みました。お店に到着し、ありつけたうどんの定食は15ドル。満腹感に浸り、さあ帰ろうと小山氏が車に戻ろうとしたところ、そこにあるはずの車が忽然と消えていました。日本のように《違法駐車のためレッカー車で移動した》との書き残しもなく、ただただ途方に暮れるしかなかったという小山氏。すると、背後から声をかけられます。そこには1人のホームレスが立っており、3ドル50セントを恵んでくれと英語で話しかけてきました。狐につままれたような状態だった小山氏は、次第に現実に起きている状況を理解し始め、さらにホームレスが言っている3ドル50セントとは、道路の向こう側にあるハンバーガーショップのメニューが3ドル50セントであることも理解します。「ああ、アレが食べたいのか。そうだ。残り5ドルを全部この人にあげて、車がどこにいったのかを聞こう」と思い立ちます。お金を手にしてすごく喜んだというホームレスは、戻ってくるとだけ言い残し、小山氏の前から姿を消しました。車も、お金もなく、不安に押し潰されそうになる小山氏でしたが、ホームレスの彼は3分たっても帰って来ません。5分たっても来ない。ようやく10分がすぎたとき、戻ってきたホームレスの手には1枚の紙切れが握られていました。ここに行け。すごく下手で、汚い字だったのですが、それを信じるしかなかった小山氏は、書かれた住所をたよりにして30分ほど歩き、無事に車がレッカーされている場所にたどり着けました。「そんな経験をしたんですが、僕はそれで“人って素敵だなって感じたんです。その紙切れはいま、きれいなフォトフレームに入れて、事務所に飾ってあります」というのが、小山氏の記憶に刻まれた「手書き」なのだそうです。
日進月歩するデジタル全盛の現代ですが、改めて「手書き」で手紙を書くという素晴らしいコミュニケーションについて、改めて見直してほしいと、それぞれのエピソードを交えた3人によるトークイベントでした。
「パーカー」について
「パーカー」は1888年創業。高級筆記具の世界において、125年以上にわたり、革新性、スタイル、独自性の高いクラフトマンシップを追及し続け、お客様に書くことの悦びを提供してきました。「パーカー」は高品質な素材を使用することで世界的に知られ、また厳格なテストを通じて、その名高い専門技術をペンに投じています。「パーカー」の象徴である“矢羽クリップ”には、未知への挑戦や新たな可能性を探し求めるなど、 志を抱く人々の道しるべでありたいというメッセージが込められています。
「パーカー」は英国王室御用達を戴くブランドです。品質を認められたものにのみ与えられる名誉ある称号ロイヤルワラント。英国王室にサービスや品物を定期的に供給する個人や企業に与えられています。現在、ロイヤルワラントを授与できるのはエリザベス女王とエジンバラ公、チャールズ皇太子の3人のみ。5年ごとに見直しが行われるため、認定を長年にわたり維持することは、王室に認められる高い品質を継続して維持していることの証にもなります。「パーカー」は1962年にエリザベス女王から、1991年にチャールズ皇太子からロイヤルワラントの認定を受け、保持し続けています。
「パーカー」はニューウェルのブランド群をこれまで牽引し、現在約150カ国で世界展開しています。「パーカー」は、洗練されたペンを使用することで、自分自身を向上させ、よりよく考えるきっかけを促すお手伝いをいたします。
【一般のお客様からのお問い合わせ先】
ニューウェル・ラバーメイド・ジャパン株式会社
0120-673-152 www.parkerpen.com
ニューウェル・ラバーメイド・ジャパン株式会社(住所:千代田区神田錦町1丁目1番地、代表取締役社長:松尾 昌典)が展開する、クラフトマンシップとデザイン革新のリーダーである高級筆記具ブランド「パーカー」が主催となり、8月31日に東京・銀座にある文房具専門店「伊東屋」でトークイベントが開催されました。そこでは、特別に来日した「パーカー」創業者の曾孫にあたるジェフリー・パーカー氏と、「パーカー」のブランドアンバサダーである放送作家の小山薫堂氏、そして会場となった「伊東屋」の代表取締役社長である伊藤明氏の3人が登壇し、それぞれが「手書き」にまつわるエピソードを披露しました。
■手書きには、そのときの感情が表れる
[画像1: http://prtimes.jp/i/19925/11/resize/d19925-11-419991-2.jpg ]
まず、放送作家という、モノを書くことを仕事にしている小山薫堂氏は、「昔はテレビの仕事は、ずっと手書きでした」と述懐。通称・テレ原と呼ばれたテレビ用の原稿用紙があり、1時間のバラエティー番組でだいたい60枚から70枚ほどを書き上げ、終わるころには洋服の袖口が真っ黒になっていたとそうです。その後、ワープロ、コンピューター、さらには小さなパソコンと化した携帯電話が登場し、「書く」という作業は飛躍的に効率化されて、楽になってはいますが、小山氏は逆に、今だからこそ「手書き」の機会が増えていると明かしました。それは「手で書いているほうが、勢いがあるんです」とのこと。頭の中にひらめいたアイディアをデジタル機器で記録するよりも、その一瞬の思いをバーっと手で書いたほうが、筆圧が強くなったり、字が荒くなったりはするが、そのほうが「勢い」が感じられ、さらにアイディアが広がっていくのだそうです。自身の日記は今も手書きだという小山氏。「手書き」だと、悲しいときは悲しい字に、うれしいときはうれしい字に、そして怒っているときは乱れたりするが、感情が字として表れることこそが「手書き」の魅力だと語りました。小山氏は旅をするとき、必ずトラベルノートを持っていくとも語ります。電車や飛行機の移動中に、いま抱えている仕事や悩み、そのときの心情を吐露するように手書きで日常を綴っており、それを後々になって読み直すことが面白いと言います。「旅に出たときに、自分のことを引いた目で改めて見るという習慣が、僕のストレス解消にもなっているんです」と、小山氏。その際は「万年筆で書いたほうが、後で読み返したときにカッコよく見えるんです。「パーカー」の「ソネット」は比較的、細い字で書けて、字もにじまず、小さなトラベルノートに書きやすいんです」。
■手書きは尊重されるべき個人的なコミュニケーションである
[画像2: http://prtimes.jp/i/19925/11/resize/d19925-11-315744-1.jpg ]
1888年、当時25歳だったジョージ・パーカー氏によって創業された「パーカー」は、エリザベス女王やチャールズ皇太子が愛用してきた英国王室御用達のブランドです。最初は小さな会社でしたが、非常に賢明で聡明な若き創業者によって、現在は世界的に認知された非常に大きなブランドに成長しました。創業者の曾孫にあたるジェフリー・パーカー氏は、手書きという「ハンドライティング」はパーソナルなコミュニケーションであり、今や当たり前となったデジタルとは両極端に位置するアナログな行為ではありますが、非常に重要な個人的経験として尊重すべきキーワードだと位置づけています。そもそもパーカー氏の家族は書くということが好きで、祖父のケネス・パーカー氏が1928年から1938年までつけていた日記が残されています。そこには、ケネス氏が当時、興味を持っていたこと、困難で難しいと感じていたことなどが示唆に富む形で書き記されており、それを読んだジェフリー氏は「非常にエモーショナルで、祖父の感情が手にとるように伝わってきて、そこから多くのことを学ぶことができました」と明かしました。当時は世界的な大恐慌の時代。祖父の悩み、立ちはだかる困難、しかし、それに立ち向かう思考が記され、その手書きの日記はジェフリー氏にとって、何ものにも勝る貴重な宝物になっているそうです。
■書いた記憶のないノートに自分の字が書かれていた
[画像3: http://prtimes.jp/i/19925/11/resize/d19925-11-770942-0.jpg ]
トークショーの会場となった「伊東屋」も1904年に創業した老舗の文房具専門店。今年で112年になる「伊東屋」の店頭では、販売する商品が時代によって変化し、進化していますが、常に新しく、しかし変わらない魅力を備えているのは万年筆だと伊藤明氏は言います。年代モノといわれる「パーカー」の万年筆は、当時は最新式のインクの入れ方をしており、一見レトロに見えるボディも美しく、そこにテクノロジーを感じると語ります。伊藤氏は「今のデジタルなテクノロジーは、いつか時代の流れで古くなることもありますが、「パーカー」の万年筆は決して古くならず、そういうモノが僕は好き」と、目を細めました。そんな伊藤氏がずっと忘れられない「手書き」にまつわる思い出は、氏が12歳のときに亡くなった父が書き残していたというノート。伊藤氏が新しい店舗を出店するとき、どうしたらいいか悩んでいました。「そんなとき、ふと、会社にある机の引き出しを開けたら、見たことのないノートが出てきたんです。そこの書かれている字を見て、まずはビックリしました。僕の書く字にそっくりなんです」。しかし、伊藤氏にこのノートで何かを書いたという記憶はありません。さらに、小学生で父親を亡くした伊藤氏は、父親の筆跡に関する記憶もありませんでした。「でもノートには、僕と同じ字で、まさに僕が悩んでいることがそのまま書いてあったんです。しかも、その悩みに対しての“答え”も書いてありました」。つまり、このノートは伊藤氏の父親が書いたものだったのです。「それを読んで、親子で書く字というのがこんなにも似ているんだということにまずは驚き、さらに同じことに悩んでいたということを知ったとき、まるで誰かに仕掛けられたドッキリかと思うほどでした」と笑いました。
■アメリカのホームレスが書いた1枚の紙切れ
さらに小山氏が披露する「手書き」に関する体験で記憶に残っているというのは、9年前のこと。滝田洋二郎が監督を務め、第81回アカデミー賞外国語映画賞、および第32回日本アカデミー賞最優秀作品賞などを受賞した2008年公開の映画『おくりびと』の脚本を担当したのが小山氏でした。アメリカのカリフォルニア州サンフランシスコ・ベイエリアの北部に位置するナパバレーで、映画の脚本を書いていた小山氏。第1稿をようやく書き終えた小山氏は、その解放感から日本食の『うどん』が恋しくなり、そのためにレンタカーを借りて、サンフランシスコにある有名な日本料理店に向かうことにしました。ただし、すぐに脚本の推敲に取りかからなくてはいけなかったこともあり、お金はそれほど持たず、とりあえず20ドル紙幣のみをポケットにねじ込みました。お店に到着し、ありつけたうどんの定食は15ドル。満腹感に浸り、さあ帰ろうと小山氏が車に戻ろうとしたところ、そこにあるはずの車が忽然と消えていました。日本のように《違法駐車のためレッカー車で移動した》との書き残しもなく、ただただ途方に暮れるしかなかったという小山氏。すると、背後から声をかけられます。そこには1人のホームレスが立っており、3ドル50セントを恵んでくれと英語で話しかけてきました。狐につままれたような状態だった小山氏は、次第に現実に起きている状況を理解し始め、さらにホームレスが言っている3ドル50セントとは、道路の向こう側にあるハンバーガーショップのメニューが3ドル50セントであることも理解します。「ああ、アレが食べたいのか。そうだ。残り5ドルを全部この人にあげて、車がどこにいったのかを聞こう」と思い立ちます。お金を手にしてすごく喜んだというホームレスは、戻ってくるとだけ言い残し、小山氏の前から姿を消しました。車も、お金もなく、不安に押し潰されそうになる小山氏でしたが、ホームレスの彼は3分たっても帰って来ません。5分たっても来ない。ようやく10分がすぎたとき、戻ってきたホームレスの手には1枚の紙切れが握られていました。ここに行け。すごく下手で、汚い字だったのですが、それを信じるしかなかった小山氏は、書かれた住所をたよりにして30分ほど歩き、無事に車がレッカーされている場所にたどり着けました。「そんな経験をしたんですが、僕はそれで“人って素敵だなって感じたんです。その紙切れはいま、きれいなフォトフレームに入れて、事務所に飾ってあります」というのが、小山氏の記憶に刻まれた「手書き」なのだそうです。
日進月歩するデジタル全盛の現代ですが、改めて「手書き」で手紙を書くという素晴らしいコミュニケーションについて、改めて見直してほしいと、それぞれのエピソードを交えた3人によるトークイベントでした。
「パーカー」について
「パーカー」は1888年創業。高級筆記具の世界において、125年以上にわたり、革新性、スタイル、独自性の高いクラフトマンシップを追及し続け、お客様に書くことの悦びを提供してきました。「パーカー」は高品質な素材を使用することで世界的に知られ、また厳格なテストを通じて、その名高い専門技術をペンに投じています。「パーカー」の象徴である“矢羽クリップ”には、未知への挑戦や新たな可能性を探し求めるなど、 志を抱く人々の道しるべでありたいというメッセージが込められています。
「パーカー」は英国王室御用達を戴くブランドです。品質を認められたものにのみ与えられる名誉ある称号ロイヤルワラント。英国王室にサービスや品物を定期的に供給する個人や企業に与えられています。現在、ロイヤルワラントを授与できるのはエリザベス女王とエジンバラ公、チャールズ皇太子の3人のみ。5年ごとに見直しが行われるため、認定を長年にわたり維持することは、王室に認められる高い品質を継続して維持していることの証にもなります。「パーカー」は1962年にエリザベス女王から、1991年にチャールズ皇太子からロイヤルワラントの認定を受け、保持し続けています。
「パーカー」はニューウェルのブランド群をこれまで牽引し、現在約150カ国で世界展開しています。「パーカー」は、洗練されたペンを使用することで、自分自身を向上させ、よりよく考えるきっかけを促すお手伝いをいたします。
【一般のお客様からのお問い合わせ先】
ニューウェル・ラバーメイド・ジャパン株式会社
0120-673-152 www.parkerpen.com
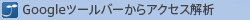

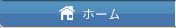
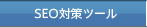
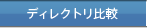

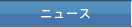



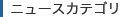
 SEO関連
SEO関連