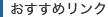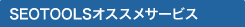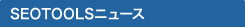「一青窈 20th ANNIVERSARY SPECIAL LIVE ~アリガ二十〜」ライブレポート
[22/10/31]
提供元:PRTIMES
提供元:PRTIMES
2002年10月30日、シングル「もらい泣き」でデビューした一青窈。20周年を迎える、まさにその日、中野サンプラザホールで「一青窈 20th ANNIVERSARY SPECIAL LIVE ~アリガ二十〜」を開催した。
[画像: https://prtimes.jp/i/19470/2743/resize/d19470-2743-7a89bc0d65b30a23c868-0.jpg ]
自ら詩を書き、歌うだけでなく、作詞家として多くのアーティストにも歌詞を提供するほか、映画や舞台で主演を務め、俳優としても活動を続けている。この記念ライブのホールロビーでは、バイリンガル絵本『ハナミズキ A Hundred Years』の原画展示も行われたが、そうした創作活動を含めると活動は多岐に渡る。
だが、当の本人はたびたび、「自分の原点はライブ」と語ってきた。学生時代にストリートで歌い始めたときから、届ける場所があるならばどこへでも出向いて歌うという姿勢は、今も変わらない。20周年の節目に、原点であるライブで一青窈は何を歌い届けたのかを記したいと思う。
オープニングは、まるで演劇の舞台かと見紛うようなシアトリカルな演出でスタートだった。夕焼けや赤ちゃんの泣き声、電車の踏切の音、そして時折聴こえてくる「愛してほしい」という切実な歌声……。音と色の織り成すステージ上の世界観へ、一気に引き込まれていった。
冒頭のノスタルジーな演出を引き継ぐように1曲目は、デビューアルバム「月天心」から「ジャングルジム」を選んだ一青。柔らかく優しく歌いながら、小さなスツールをジャングルジムに見立てて、ときには登ったりもする。そうやって歌詞の世界観を全身で、ときには演じるように表現し尽くすのが彼女のスタイルだ。
続くアップテンポの「Lesson」では、自然と手拍子が沸き起こった。歌の中で「二十周年、あなたのおかげです」「最後まで楽しんで」と観客に謝意を伝えつつ、ダンサーを従えて軽快にステップを踏む。しなやかな動きと伸びやかな歌声、そして「まだ20年しか歌ってないんだけど」という言葉に、彼女の音楽活動への強い思いをかいま見た気がした。
この20周年記念ライブは、大勢のアーティストを招いた15周年の記念ライブと良い意味で対照的だったように思う。バンドマスターの武部聡志をはじめ、これまで長年ステージを共にしてきたメンバーという最小限のスタイルで、豊潤なバンドサウンドと真心のこもった歌声を真正面から観客に届けるものだった。
3曲を歌い、初めてのMCで「ずっと支えてくれたメンバーです」とステージ上の仲間紹介した一青。気心の知れた面々へ、トークテーマ「印象に残るアルバイト」をいきなり投げかけてバンドマンたちを少し戸惑わせたりするのも彼女らしい。
実は、この無茶ぶりにはちゃんと意味があった。「私は26歳でデビューしましたが、その前はアルバイトでCMの歌などを歌わせてもらっていて」と、過去の逸話を披露。人気ゲーム「三国無双」のエンディングテーマを中国語で歌う仕事も担当したという。
4曲目の「生路〜MAZE」では、その思い出のナンバーを歌唱。大人っぽいジャジーなサウンドと中国語という少し耳に新しい響きがが相まって、どこかロマンチックな歌模様を描くのだから音楽というのは不思議だ。
5曲目の「かたつむり」は、コロナ禍で感じたことを詩にしたため、松任谷由実が曲を付けたものだ。“大の字になって”と歌うくだりでは、ステージ上で実際に大の字に寝転がって歌ってみせた一青。歌はこんなに自由であっていいものなのかと、ハッとさせられた。
この「かたつむり」や、まどろみの中に佇んでいるようにドリーミーな7曲目「腕枕」。バンドサウンドと言葉のおしゃれなコラボレーションに心ときめく15曲目「カノン」などは、12月にリリースされる(なんと8年ぶり!)アルバム「一青尽図」に収録予定の楽曲だ。20周年を祝おうと会場に足を運んでくれたファンへ、いち早く新曲というプレゼントを届けるという彼女の粋な計らいだったに違いない。
前半戦が落ち着いた大人の時間だったとすれば、目もくらむようなピンク色の閃光が始まりを告げた10曲目「ピンクフラミンゴ」。ハードなロックに合わせてシャウトするように歌う11曲「犬」へとなだれ込む中盤は、パワフルで遊び心に溢れたセクションだ。歌いながら、サインボールを客席に次々に投入れた後、「46歳には、これはしんどい」と会場を笑わせることも忘れない。このライブのために書き下ろした「窈ちゃんのおかんむり絵描き歌」は、よく書き間違えられる“窈”という字をネタにしたユニークなナンバーで、こうした茶目っ気たっぷりなところも一青が愛される理由なのだろう。
そうした遊び心と同時に、中盤では、一青窈という表現者の多彩さをいかんなく発揮してみせた。なかでも、濃い青一色に染め上げられた空間に佇み、重厚なバンドサウンドに乗せて、願い祈るように歌う「月天心」は圧倒的だった。深い海の底に息をひそめて居るような、それでいて夜の闇の中を浮遊しているような不思議な体験を、この曲を介して観客は共有したのではないだろうか。
余韻に浸っていると、MCで「初めて人前で心を込めて歌った歌」について話し始めた。「修学旅行のバスの中で、窈ちゃんも何か歌いなよとマイクが回ってきました」と、当時を振り返る一青。
人に向けて歌うという“歌人生”で初めての歌「あなた」(小坂明子のカバー)から、終盤戦の始まりを告げるメドレーはスタートした。続く「もらい泣き」でエキゾチックな雰囲気を漂わせたかと思えば、「他人の関係」では艶やかに。「江戸ポルカ」で、オーディエンスに向けて振り付けレクチャーを行った後、会場みんなで振り付けを楽しみ、再び20年前のこの日にリリースされた「もらい泣き」の拍手という熱気の中でメドレーは帰結した。
「今日までやって来れたのは皆さんのおかげです」と改めて思いを伝えた一青。
「20年、音楽の世界で一緒にやってきた(森山)直太朗さんが曲を書いてくれました。節目に書いてくれて嬉しい」と紹介した「耳をすます」が本編ラストのナンバーだ。本公演に先駆け、本公演は「耳をすます」をしっかりと届ける演出にしたいと語っていた一青。そのために、「今日のために書いた」という詩の朗読から、歌へと入っていった。旅が好きな僕が、さまざまな土地を訪ね歩くなかで気付きを得ていくという内容は、歌の内容ともリンクするものだ。
そして、この歌唱を目にしたとき、オープニングのシアトリカルな演出や「愛してほしい」の歌声を含め、ライブで散りばめられていたすべての点と点とが糸で繋がっていくのを感じて肌が粟立った。
実は、この記念ライブの本編に自身最大のヒット曲「ハナミズキ」はラインナップされなかった。あるとき、「予定調和は苦手なんです」と言い、「ハナミズキ」を特別扱いしないと笑った彼女。言葉通りに受け取れば、心地よい一種の裏切りの演出と見ることもできる。
でも、それこそ一青窈の、ことばのマジックにまんまと引っ掛かったようなものだ。彼女自身、胸が押しつぶされそうになり、泣きながら綴ったという「耳をすます」に溢れる真心と誠実さは、いまもっとも彼女が届けたい思いに違いない。何度も「頑張ったね、大丈夫」と励まし、「愛します、愛しています」と寄り添う温かな声は、きっとどこかで膝を抱えてうつむいている誰かに届くと信じたい、いや信じられる……そんな気持ちにさせてくれる本編の終わりだった。
その想いを受け取った観客は、ステージからこの日の主役が立ち去った後も、拍手を止めることはなかった。
再び、するすると幕が上がると、正座をしてアンコールの声に応える一青の姿がそこにあった。真っ白な衣装から和柄模様のオリエンタルなドレスへと着替え、足元にも届きそうな長い髪をポニーテール上に束ねている。
アンコール1曲目「アリガ十々」の温かで多幸感の溢れるナンバーで、この瞬間を祝祭した。そして、オールラストに彼女が選んだのは、「ハナミズキ」だった。情感込めてに歌いあげる一青の声に、バンドメンバーのコーラスが重なり荘厳さが際立つアレンジとなっていた。歌の途中、長い髪にダンサーたちが鋏を入れ、切った髪を高々と持ち上げて去る演出もまたどこか神聖な儀式を彷彿とさせ、視覚的にも厳かさが伝わる見事な演出だった。
その名曲を生み出した、作曲家のマシコタツロウがサプライズゲストとして花束を携えて登壇。観客とともに「窈ちゃん、20周年おめでとうございます」と、声を合わせて20周年祝い、ねぎらった。
カーテンコールのあと、ひとりステージに残った一青は、感極まった様子で「ありがとうございました。また遊びに来てください」と言葉短くお礼を述べ、舞台を後にした。20周年を迎えてなお、こんなに不器用でシャイなところもまた、彼女の素敵な一面。ファンはそれを分かっているからこそ、そんな一青の誠実な歌に涙し、惜しみない拍手を贈るのだろう。
一夜限りの記念ライブは終わったが、12月には、「私重奏」以来となる8枚目のオリジナルアルバム「一青尽図」がリリースとなる。本公演で披露された松任谷由実や森山直太朗らが手がけた曲のほか、Charaやゴスペラーズの酒井雄二、長澤知之など、一青とゆかりのある豪華なアーティストとのコラボが多数叶った作品だ。
ライブの途中、「まだ20年しか歌っていない」と語った一青が、この先、どんな歌で心の奥に触れ魂を揺さぶるのか……。そんな期待感がますます高まる充実のライブパフォーマンスだった。
文:橘川 有子
写真:尾形隆夫
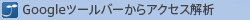

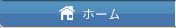
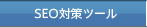
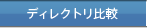

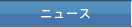




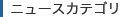
 SEO関連
SEO関連