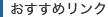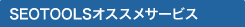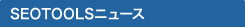シティ・オブ・ロンドンの独特な選挙制度【フィスコ世界経済・金融シナリオ分析会議】
[20/02/26]
提供元:株式会社フィスコ
提供元:株式会社フィスコ
注目トピックス 経済総合
■シティと大ロンドン、自治体系の違い
前回の記事では「大ロンドン」と「シティ・オブ・ロンドン(以下、シティ)」の違いについて述べてきた。本記事では、あまり掘り下げられなかったシティ独特の自治について見てみたいと思う。
シティは歴史がブリテン島の中でも一番古い政体になるため、伝統とこれまでの妥協と折衷の積み重ねの果てに、非常に複雑な選挙方法が使用されている。簡単に述べると、中世のようなギルド、近代的な企業、そして個人に授与する称号などが非常に複雑な形で絡み合う。
実は大ロンドンにおける最初の市長は2000年になって初めて選ばれたが、シティでは1000年ほど前から合計700人以上の市長を選出している。これは、大ロンドンがこれまで伝統的な地区(庶民院選挙区に近いもの)ごとでの自治を長らく行っていたため、いわゆる統一的なロンドンという自治体ができたのは1965年が最初であり、これも1986年に一回解散した(ただし、最初の統一的なロンドンの自治体には個別の市長選はなく、どちらかというと庶民院における首相選出のように、党派筆頭の議員がこの自治体議員会合のリーダーになるという形だった)。
■権利・権力の基盤
ここでイギリスの根本的な法理論をおさらいすると、イギリス議会(貴族院と庶民院)の権利権力は「王権(法律的な概念上、国王国家とそれが内包するものを「The Crown(ザ・クラウン)」と呼び、ここでは便宜的に王権と書く)」から付与された。そしてこの王権は元々神から来たもので、歴史的な経緯でこれを議会が修正を加えることができるという法的理論になっている。しかし、シティはイギリス全体と考えが違う。シティが最初存在し始めたときからの記録は存在しない。そのため、記録を超越するほどの昔から存続し、存在してきた権利は「太古の昔(Time Immemorial、「記憶できないほどの時から」)」の権威によって存在するということになっている。
マグナカルタ(大憲章)の第13条には「……そしてロンドン(当時大ロンドンに該当する政体はないため、ロンドンと言えばシティを指す)のその太古から存在する自由と慣習、陸上でも水上でもこれを認めることとする」と記される。よって、相当古い文書でもシティの権利・権威を認めているということになり、むしろこういうものでしか相対的に存在していたということが確認できない。余談ではあるが、これは日本の皇室の権威がどこからきているのかという考えと理論に通じるものがある。
■シティの「議会」
前回の記事からの続きだが、シティはその権威権利を守ることに熱心であり、そして太古の昔から続く慣習を守ることにも余念がないため、イギリスで適用される選挙法はシティに適用されないことを再度ここに記す。
実際の選挙の概要としては、以下の通りである。
・シティの選挙では事実上、四分の三ほどの票は近代的な企業が有する。
・残りは法律上の「住民」がその票を有する。
・企業が大きければ大きいほど(従業員数)、それだけ票をシティの自治政府「コーポレーション・オブ・ロンドン」(以下、コーポレーション)からもらう。
・その企業は、選んだ従業員にその票を持たせる(ほとんどの従業員は物理的な住民ではなく、高い確率でシティの外にいる住民)。
・コモン・カウンシル(市民議会、シティの「下院」に値する、そしてコーポレーションの中心)の評議員の内20名ほどが住民の票からなるが、残りの80ほどが企業票によって選ばれている。
なお、企業の従業員数に応じて票を授与する理由としては、毎日住民一人あたり43人ほどがシティに流入して働いているため、彼らがシティで働くことを、シティでビジネスがやりやすいことにかかっているからとなっている。よって、従業員の権利を企業が代表するという論理になっている。
■シティの市長になるには
シティの自治体系を感覚的に理解するには、市長になるためのプロセスを見るのが一番簡単だと筆者は感じている。よって、上記の議会についての項目を念頭に、「市長選」にいたるまでの過程を読み解いていただければと思う。
大ロンドンの市長になるにはイギリスか英国連邦の国民で、最低1年在住していて、そして市長選で勝つことが必要である。一方、シティの市長(The Right Honourable, The Lord Mayor of London、市長卿と大雑把に訳せる)は、そこまで単純でない。
市長になるには、元々「シェリフ(歴史的には判事と国王の代理徴税官)」である必要がある。シェリフになるには「オルダーマン」(長老参事会員、事実上の「上院」、シティの各地区から一人選ばれる)である必要がある。オルダーマンになるには、自由市民(Freeman)になる必要があり、この権利は長老参事会から授与される。
長老参事会から自由市民権を貰うのがやや難しいと感じた場合は、他にも自由市民になる方法がある。主にこれは中世的なギルド(正式には「Livery Companies」リヴァリ・カンパニーであるが、本稿ではギルドと呼ぶ)から授与してもらう方法である。
シティには現在108ほどの「ギルド」が存在し、これも非常にユニークである。例として、薬屋(医療系の資格も授与する)、魚屋、石工、絹物商、科学機器、造船、車大工、二つの蝋燭屋、公認会計士、金細工(今でも硬貨の試験など実務がある)、矢製造工(今は慈善協会)、タクシー(タクシー運転者の正式名称は「ハックニー・馬車御者」、ギルドはタクシー免許の授与を行う)が挙げられる。このようなギルドに入るには、職業資格を有しているか、特に慈善協会になっているギルドでは二人以上の推薦で入ることができる。なお、ギルドを設立するには長老参事会の同意が必要であるため、勝手にギルドを作って自分に自由市民権を付与することはできない。
最終的には、4つの住民地区か、21の企業地区から長老参事会員として立候補をすることができる。なお、次の段階のシェリフになるには、ギルドによって長老参事会から二人が選ばれる。
そして最終的にシティ市長になるためには、シェリフの中から長老参事会によって選出される(よって、直接住民票ではない)。
なお、この非常に複雑なシステムを通じてシティの市長になったとしても、シティの市長は無給で、在任期間も1年である。シティのビジネス的な利便さなどをアピールするために、海外に行くことが多く、式典やシティ独自の伝統行事やそれに付随する市長のコストは全部市長自身で払うことになっている。
地経学アナリスト 宮城宏豪
幼少期から主にイギリスを中心として海外滞在をした後、英国での工学修士課程半ばで帰国。日本では経済学部へ転じ、卒業論文はアフリカのローデシア(現ジンバブエ)の軍事支出と経済発展の関係性について分析。大学卒業後は国内大手信託銀行に入社。実業之日本社に転職後、経営企画と編集(マンガを含む)を担当している。これまで積み上げてきた知識をもとに、日々国内外のオープンソース情報を読み解き、実業之日本社やフィスコなどが共同で開催している「フィスコ世界金融経済シナリオ分析会議」では、地経学アナリストとしても活躍している。
<SI>
前回の記事では「大ロンドン」と「シティ・オブ・ロンドン(以下、シティ)」の違いについて述べてきた。本記事では、あまり掘り下げられなかったシティ独特の自治について見てみたいと思う。
シティは歴史がブリテン島の中でも一番古い政体になるため、伝統とこれまでの妥協と折衷の積み重ねの果てに、非常に複雑な選挙方法が使用されている。簡単に述べると、中世のようなギルド、近代的な企業、そして個人に授与する称号などが非常に複雑な形で絡み合う。
実は大ロンドンにおける最初の市長は2000年になって初めて選ばれたが、シティでは1000年ほど前から合計700人以上の市長を選出している。これは、大ロンドンがこれまで伝統的な地区(庶民院選挙区に近いもの)ごとでの自治を長らく行っていたため、いわゆる統一的なロンドンという自治体ができたのは1965年が最初であり、これも1986年に一回解散した(ただし、最初の統一的なロンドンの自治体には個別の市長選はなく、どちらかというと庶民院における首相選出のように、党派筆頭の議員がこの自治体議員会合のリーダーになるという形だった)。
■権利・権力の基盤
ここでイギリスの根本的な法理論をおさらいすると、イギリス議会(貴族院と庶民院)の権利権力は「王権(法律的な概念上、国王国家とそれが内包するものを「The Crown(ザ・クラウン)」と呼び、ここでは便宜的に王権と書く)」から付与された。そしてこの王権は元々神から来たもので、歴史的な経緯でこれを議会が修正を加えることができるという法的理論になっている。しかし、シティはイギリス全体と考えが違う。シティが最初存在し始めたときからの記録は存在しない。そのため、記録を超越するほどの昔から存続し、存在してきた権利は「太古の昔(Time Immemorial、「記憶できないほどの時から」)」の権威によって存在するということになっている。
マグナカルタ(大憲章)の第13条には「……そしてロンドン(当時大ロンドンに該当する政体はないため、ロンドンと言えばシティを指す)のその太古から存在する自由と慣習、陸上でも水上でもこれを認めることとする」と記される。よって、相当古い文書でもシティの権利・権威を認めているということになり、むしろこういうものでしか相対的に存在していたということが確認できない。余談ではあるが、これは日本の皇室の権威がどこからきているのかという考えと理論に通じるものがある。
■シティの「議会」
前回の記事からの続きだが、シティはその権威権利を守ることに熱心であり、そして太古の昔から続く慣習を守ることにも余念がないため、イギリスで適用される選挙法はシティに適用されないことを再度ここに記す。
実際の選挙の概要としては、以下の通りである。
・シティの選挙では事実上、四分の三ほどの票は近代的な企業が有する。
・残りは法律上の「住民」がその票を有する。
・企業が大きければ大きいほど(従業員数)、それだけ票をシティの自治政府「コーポレーション・オブ・ロンドン」(以下、コーポレーション)からもらう。
・その企業は、選んだ従業員にその票を持たせる(ほとんどの従業員は物理的な住民ではなく、高い確率でシティの外にいる住民)。
・コモン・カウンシル(市民議会、シティの「下院」に値する、そしてコーポレーションの中心)の評議員の内20名ほどが住民の票からなるが、残りの80ほどが企業票によって選ばれている。
なお、企業の従業員数に応じて票を授与する理由としては、毎日住民一人あたり43人ほどがシティに流入して働いているため、彼らがシティで働くことを、シティでビジネスがやりやすいことにかかっているからとなっている。よって、従業員の権利を企業が代表するという論理になっている。
■シティの市長になるには
シティの自治体系を感覚的に理解するには、市長になるためのプロセスを見るのが一番簡単だと筆者は感じている。よって、上記の議会についての項目を念頭に、「市長選」にいたるまでの過程を読み解いていただければと思う。
大ロンドンの市長になるにはイギリスか英国連邦の国民で、最低1年在住していて、そして市長選で勝つことが必要である。一方、シティの市長(The Right Honourable, The Lord Mayor of London、市長卿と大雑把に訳せる)は、そこまで単純でない。
市長になるには、元々「シェリフ(歴史的には判事と国王の代理徴税官)」である必要がある。シェリフになるには「オルダーマン」(長老参事会員、事実上の「上院」、シティの各地区から一人選ばれる)である必要がある。オルダーマンになるには、自由市民(Freeman)になる必要があり、この権利は長老参事会から授与される。
長老参事会から自由市民権を貰うのがやや難しいと感じた場合は、他にも自由市民になる方法がある。主にこれは中世的なギルド(正式には「Livery Companies」リヴァリ・カンパニーであるが、本稿ではギルドと呼ぶ)から授与してもらう方法である。
シティには現在108ほどの「ギルド」が存在し、これも非常にユニークである。例として、薬屋(医療系の資格も授与する)、魚屋、石工、絹物商、科学機器、造船、車大工、二つの蝋燭屋、公認会計士、金細工(今でも硬貨の試験など実務がある)、矢製造工(今は慈善協会)、タクシー(タクシー運転者の正式名称は「ハックニー・馬車御者」、ギルドはタクシー免許の授与を行う)が挙げられる。このようなギルドに入るには、職業資格を有しているか、特に慈善協会になっているギルドでは二人以上の推薦で入ることができる。なお、ギルドを設立するには長老参事会の同意が必要であるため、勝手にギルドを作って自分に自由市民権を付与することはできない。
最終的には、4つの住民地区か、21の企業地区から長老参事会員として立候補をすることができる。なお、次の段階のシェリフになるには、ギルドによって長老参事会から二人が選ばれる。
そして最終的にシティ市長になるためには、シェリフの中から長老参事会によって選出される(よって、直接住民票ではない)。
なお、この非常に複雑なシステムを通じてシティの市長になったとしても、シティの市長は無給で、在任期間も1年である。シティのビジネス的な利便さなどをアピールするために、海外に行くことが多く、式典やシティ独自の伝統行事やそれに付随する市長のコストは全部市長自身で払うことになっている。
地経学アナリスト 宮城宏豪
幼少期から主にイギリスを中心として海外滞在をした後、英国での工学修士課程半ばで帰国。日本では経済学部へ転じ、卒業論文はアフリカのローデシア(現ジンバブエ)の軍事支出と経済発展の関係性について分析。大学卒業後は国内大手信託銀行に入社。実業之日本社に転職後、経営企画と編集(マンガを含む)を担当している。これまで積み上げてきた知識をもとに、日々国内外のオープンソース情報を読み解き、実業之日本社やフィスコなどが共同で開催している「フィスコ世界金融経済シナリオ分析会議」では、地経学アナリストとしても活躍している。
<SI>
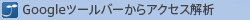

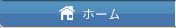
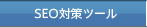
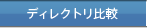

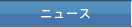



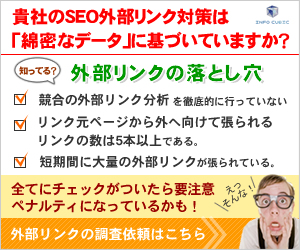
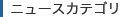
 SEO関連
SEO関連