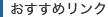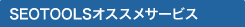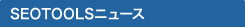日米司厨士協会の連携と日本人シェフ稲田英男が生んだ 「デミグラスソース」開発秘話 洋食によって日本が最大消費国となった洋風ソースの王様
[09/05/27]
提供元:PRTIMES
提供元:PRTIMES
今年は日本の開国150周年、それは「洋食150周年」でもあります。初めて西洋料理に遭遇した当時の日本人は大きなショックを受けると同時に、強いあこがれをもってそれを吸収しようとしました。しかも日本人は、西洋料理をそのまま取り入れたのではなく、ご飯に合うように作り変えて、『洋食』という独自の食文化を作りあげたのです。それを支えたのが洋風ソースの国産化でした。
ハインツ日本(本社:東京都台東区、代表取締役社長:前田英広)は1970年に3大洋風ソースの1つ、デミグラスソースを発売。以来、業務用・家庭用のいずれにおいてもトップシェアを維持しながら、日本の洋食文化を支えてまいりました。デミグラスソースはフランス生まれですが、いまや日本が世界で最大の消費国になっています。それは日本で『洋食』文化が発展し、洋食を通じてデミグラスソースが日本人の大好きなソースになったからに他なりません。
ハインツ日本のデミグラスソース開発の裏には、日米司厨士協会※1 の連携と、開発を担当したシェフの稲田英男(故人)の存在がありました。洋食150周年にあたり、洋食と洋風ソースの魅力をお伝えする本シリーズの第2回目は、この洋風ソースの王様、「デミグラスソース」のお話です。
■ 日米司厨士協会トップの連携による、稲田英男のハインツ入社
稲田は1933年、下関に生まれました。丸の内ホテルの厨房で修行していた時代に、ホテルの総料理長で全日本司厨士協会の初代会長も務めていた斉藤文次郎に見込まれ、協会の第1回ヨーロッパ使節団に参加しました。その稲田を商品開発担当シェフとして採用したのが、ハインツ日本でした。
ハインツ日本は米国HJハインツ社の合弁会社として、1961年に創業しました。当初は米国の商品を輸入してそのまま販売していましたが、業績が思うように伸びません。そこで、親会社のシェフで米国司厨士協会の会長も務めるポール・レスキューが来日し、日本ではどんな商品なら売れるのか、その調査を開始しました。このとき彼を助けたのが、同じ司厨士協会の会長という立場でレスキューと交友関係のあった斎藤文次郎氏でした。
二人は斎藤氏の案内で数週間、毎日のように日本のレストランを食べ歩きます。その結果、「日本で成功するには、日本人の舌に合った独自の商品の開発が必要だ」という結論に至ったレスキューは、日本人シェフの仲介を斎藤氏に依頼し、斎藤氏は自分の部下である稲田を紹介したのでした。稲田はヨーロッパから帰国したばかりでした。
■ 「デミ=半分、グラス=鏡」がデミグラスソースの語源
ハインツ日本に入社した稲田は、さっそく商品化の候補を検討しました。そして、最初に注目したのがデミグラスソースでした。
デミグラスソースを厨房でつくるには、まず牛の骨やスジ肉、香味野菜などでダシ(フォン)をとり、別に小麦粉と脂を焦がさないように微妙な温度調整をしながら長時間、炒めてブラウンルゥを作ります。このフォンとブラウンルゥをあわせてソースエスパニョールをつくり、それを煮詰めます。半分まで丁寧に煮詰めることで照りが出て鏡のような光沢が出ることから、フランス語の“半分=デミ”と“鏡=グラス”を合わせてデミグラスソースという名前がつけられたのです。
このように膨大な手間・時間・コストがかかるため、稲田自身も「デミグラスソースが最初からあったら、いつでも料理にとりかかれるのに」という思いを抱いていました。当時の日本のホテルやレストランも数週間かけてつくっていましたから、必ず需要があると見抜いたのです。稲田は米国のハインツ本社でも着手していなかったこのソースの商品化に着手しました。
■ 外国にもお手本のなかったデミグラスソースの商品化に成功
気さくで温和な人柄であった稲田は、仕事では緻密で妥協を許しませんでした。そしてシェフであるからこそ、限りなく厨房に近い作り方にこだわりつつ、シェフでありながら、それを工場の生産工程に置き換えるという困難な作業に挑戦したのです。
特にハインツのデミグラスソースの大きな特長であるブラウンルゥの製造は困難を極めましたが、和菓子の餡(あん)を煉るのにも使われていたレオニーダという機械の導入により問題を解決。ついに1970年に、業務用デミグラスソースの缶詰の発売にこぎつけました。そして 1972年には、家庭用のデミグラスソースを発売したのです。
1970年は大阪で万国博覧会が開催された年でした。ファストフードやファミリーレストランも相次いで1号店を開店し、日本人にとって「洋食」は一層身近なものになりました。それとともに、デミグラスソースの需要も一気に高まります。時代の要請を受けてハインツ日本のデミグラスソースは大きく売上を伸ばし、いまやホテルやレストラン、そして家庭でも、日本人に最も愛される洋風ソースの1つとなったのです。
■ いまや発祥の地、フランスよりも日本で愛される洋風ソースの王様
実はデミグラスソースがこれほど愛され、消費されている国は日本以外にはありません。もともとはフランスの宮廷料理に起源をもち、約200年間、高級フランス料理(グランドキュイジーヌ)のソースの主流として一世を風靡しました。しかし1970年代に、いわゆるヌーベルキュイジーヌ運動が起こると、日本的な“素材を生かす料理法”に関心が高まり、ソースの主流もデミグラスソースから「ルゥを使わずフォンから作るソース」に移ってしまったのです。発祥の地でもほとんど使われなくなったデミグラスソースが“ガラパゴス現象化”して、今も日本で独自の発展を遂げているのは、「洋食」という独自の文化が発展したからに他なりません。
*本リリースは、現在の当社シェフチームのリーダー、横田の話をもとに広報でまとめました。
次回はアメリカを象徴する洋風ソース「ケチャップ」のお話で、配信は6月17日頃の予定です。
【ハインツ日本シェフチーム リーダー横田好充より】
『最近、煮込みハンバーグがブームと言われています。ハンバーグと言えば3大洋食に挙げる方も多く、特にお子様には人気のメニューですが、焼きハンバーグが主流だったのに対し、煮込みの人気が高まっている理由の1つはデミグラスソースの美味しさにあると思います。
またソースがたっぷりでご飯に合うことから、カレーライス、ハヤシライスに続いて、煮込みハンバーグライスが登場する可能性もあるでしょう』
ハインツ日本では稲田英男の系譜をひいて、プロのシェフが社員として商品開発にあたるという味作りの伝統があります。現在はシェフチームがその役割を担っています。
ハインツ日本(本社:東京都台東区、代表取締役社長:前田英広)は1970年に3大洋風ソースの1つ、デミグラスソースを発売。以来、業務用・家庭用のいずれにおいてもトップシェアを維持しながら、日本の洋食文化を支えてまいりました。デミグラスソースはフランス生まれですが、いまや日本が世界で最大の消費国になっています。それは日本で『洋食』文化が発展し、洋食を通じてデミグラスソースが日本人の大好きなソースになったからに他なりません。
ハインツ日本のデミグラスソース開発の裏には、日米司厨士協会※1 の連携と、開発を担当したシェフの稲田英男(故人)の存在がありました。洋食150周年にあたり、洋食と洋風ソースの魅力をお伝えする本シリーズの第2回目は、この洋風ソースの王様、「デミグラスソース」のお話です。
■ 日米司厨士協会トップの連携による、稲田英男のハインツ入社
稲田は1933年、下関に生まれました。丸の内ホテルの厨房で修行していた時代に、ホテルの総料理長で全日本司厨士協会の初代会長も務めていた斉藤文次郎に見込まれ、協会の第1回ヨーロッパ使節団に参加しました。その稲田を商品開発担当シェフとして採用したのが、ハインツ日本でした。
ハインツ日本は米国HJハインツ社の合弁会社として、1961年に創業しました。当初は米国の商品を輸入してそのまま販売していましたが、業績が思うように伸びません。そこで、親会社のシェフで米国司厨士協会の会長も務めるポール・レスキューが来日し、日本ではどんな商品なら売れるのか、その調査を開始しました。このとき彼を助けたのが、同じ司厨士協会の会長という立場でレスキューと交友関係のあった斎藤文次郎氏でした。
二人は斎藤氏の案内で数週間、毎日のように日本のレストランを食べ歩きます。その結果、「日本で成功するには、日本人の舌に合った独自の商品の開発が必要だ」という結論に至ったレスキューは、日本人シェフの仲介を斎藤氏に依頼し、斎藤氏は自分の部下である稲田を紹介したのでした。稲田はヨーロッパから帰国したばかりでした。
■ 「デミ=半分、グラス=鏡」がデミグラスソースの語源
ハインツ日本に入社した稲田は、さっそく商品化の候補を検討しました。そして、最初に注目したのがデミグラスソースでした。
デミグラスソースを厨房でつくるには、まず牛の骨やスジ肉、香味野菜などでダシ(フォン)をとり、別に小麦粉と脂を焦がさないように微妙な温度調整をしながら長時間、炒めてブラウンルゥを作ります。このフォンとブラウンルゥをあわせてソースエスパニョールをつくり、それを煮詰めます。半分まで丁寧に煮詰めることで照りが出て鏡のような光沢が出ることから、フランス語の“半分=デミ”と“鏡=グラス”を合わせてデミグラスソースという名前がつけられたのです。
このように膨大な手間・時間・コストがかかるため、稲田自身も「デミグラスソースが最初からあったら、いつでも料理にとりかかれるのに」という思いを抱いていました。当時の日本のホテルやレストランも数週間かけてつくっていましたから、必ず需要があると見抜いたのです。稲田は米国のハインツ本社でも着手していなかったこのソースの商品化に着手しました。
■ 外国にもお手本のなかったデミグラスソースの商品化に成功
気さくで温和な人柄であった稲田は、仕事では緻密で妥協を許しませんでした。そしてシェフであるからこそ、限りなく厨房に近い作り方にこだわりつつ、シェフでありながら、それを工場の生産工程に置き換えるという困難な作業に挑戦したのです。
特にハインツのデミグラスソースの大きな特長であるブラウンルゥの製造は困難を極めましたが、和菓子の餡(あん)を煉るのにも使われていたレオニーダという機械の導入により問題を解決。ついに1970年に、業務用デミグラスソースの缶詰の発売にこぎつけました。そして 1972年には、家庭用のデミグラスソースを発売したのです。
1970年は大阪で万国博覧会が開催された年でした。ファストフードやファミリーレストランも相次いで1号店を開店し、日本人にとって「洋食」は一層身近なものになりました。それとともに、デミグラスソースの需要も一気に高まります。時代の要請を受けてハインツ日本のデミグラスソースは大きく売上を伸ばし、いまやホテルやレストラン、そして家庭でも、日本人に最も愛される洋風ソースの1つとなったのです。
■ いまや発祥の地、フランスよりも日本で愛される洋風ソースの王様
実はデミグラスソースがこれほど愛され、消費されている国は日本以外にはありません。もともとはフランスの宮廷料理に起源をもち、約200年間、高級フランス料理(グランドキュイジーヌ)のソースの主流として一世を風靡しました。しかし1970年代に、いわゆるヌーベルキュイジーヌ運動が起こると、日本的な“素材を生かす料理法”に関心が高まり、ソースの主流もデミグラスソースから「ルゥを使わずフォンから作るソース」に移ってしまったのです。発祥の地でもほとんど使われなくなったデミグラスソースが“ガラパゴス現象化”して、今も日本で独自の発展を遂げているのは、「洋食」という独自の文化が発展したからに他なりません。
*本リリースは、現在の当社シェフチームのリーダー、横田の話をもとに広報でまとめました。
次回はアメリカを象徴する洋風ソース「ケチャップ」のお話で、配信は6月17日頃の予定です。
【ハインツ日本シェフチーム リーダー横田好充より】
『最近、煮込みハンバーグがブームと言われています。ハンバーグと言えば3大洋食に挙げる方も多く、特にお子様には人気のメニューですが、焼きハンバーグが主流だったのに対し、煮込みの人気が高まっている理由の1つはデミグラスソースの美味しさにあると思います。
またソースがたっぷりでご飯に合うことから、カレーライス、ハヤシライスに続いて、煮込みハンバーグライスが登場する可能性もあるでしょう』
ハインツ日本では稲田英男の系譜をひいて、プロのシェフが社員として商品開発にあたるという味作りの伝統があります。現在はシェフチームがその役割を担っています。
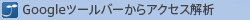

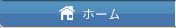
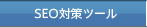
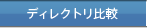

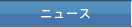



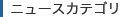
 SEO関連
SEO関連