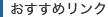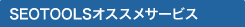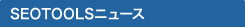微生物が作った有機液肥の性能をトマト水耕栽培で実証
[23/10/02]
提供元:PRTIMES
提供元:PRTIMES
廃棄物中の窒素のアップサイクルで資源循環に貢献
・食品加工廃水を有機液肥に変換し農業利用
・市販の化学液肥と同等の効果
・微生物がバイオフィルムを形成してトマトの根を守る
[画像1: https://prtimes.jp/i/113674/43/resize/d113674-43-26df85b24ee11b7d990d-0.png ]
概 要
国立研究開発法人 産業技術総合研究所(以下「産総研」という)環境創生研究部門 佐藤 由也 主任研究員、稲葉 知大 主任研究員、羽部 浩 副研究部門長は、株式会社 アイエイアイ(以下「IAI」という)赤地 拓澄 研究員、静岡県工業技術研究所 (以下「静岡工技研」という)室伏 敬太 上席研究員、沼津工業技術支援センター(以下「沼津工技セ」という)高木 啓詞 主任研究員、静岡大学 二又 裕之 教授らと共同で、微生物による分解活性を利用して食品加工廃水から作った有機液肥が、トマト水耕栽培で実用可能なことを実証しました。
IAIは有機液肥の製造装置を開発し、産総研らと有機液肥の製造方法を確立しました。しかし、有機液肥の性能の評価はできていませんでした。製造した有機液肥と市販の化学液肥の性能比較のため、トマトの水耕栽培を行いました。一般的に、栄養成分量を自由に決められる化学肥料の方が、有機肥料よりも植物の成長効率が高いことが知られています。本研究で製造した有機液肥は、化学液肥と比較して、植物体を約10%大きく成長させ、市販の化学肥料と同等の施肥効果を示しました。この有機液肥は微生物を含んでいます。微生物の一部がトマトの根に定着してバイオフィルムを形成することで、他の微生物の感染を防ぐ可能性が示唆されました。本技術は、廃棄物由来の肥料を利用することで、窒素資源循環を促し、持続可能な社会の実現に貢献します。
この研究成果の詳細は、2023年9月29日(日本時間)に「Applied Microbiology and Biotechnology」誌に掲載されます。
下線部は【用語解説】参照
※本プレスリリースでは、化学式や単位記号の上付き・下付き文字を、通常の文字と同じ大きさで表記しております。
PR TIMESのシステムでは特殊文字は使用できないため、正式な表記とは異なることご留意ください。
正式な表記でご覧になりたい方は、産総研WEBページ(https://www.aist.go.jp/aist_j/press_release/pr2023/pr20230929/pr20230929.html)をご覧ください。
研究の社会的背景
持続可能な社会の実現には、革新的な資源循環技術の開発が必要です。IAIでは、微生物が有機物を分解することを利用して、食品加工廃水から有機液肥を製造する技術の開発に取り組んできました。
一般的に、化学肥料は、栄養成分の量を自由に調整できるため、食品残渣などを原料とした有機肥料と比べて植物の成長効率が高いことで知られています。IAIが製造した有機液肥は、トマトなどの水耕栽培に利用できます。しかし、市販の化学液肥と比較した場合の施肥効果の違いや特徴はわかっていませんでした。
研究の経緯
産総研は、次世代シークエンサーを用いた菌叢(きんそう)解析技術を用い、廃水処理装置や自然環境などを対象にさまざまな菌叢を解明し、有害物質の分解・除去に関わる微生物を特定してきました(2019年5月13日 産総研プレス発表[1]、2021年9月9日 産総研プレス発表[2])。
資源循環や環境負荷低減の観点から、IAIではタンパク質を多く含む魚の煮汁などの水産加工廃水を原料とし、微生物を用いて、窒素系の有機液肥の製造を可能にする装置を開発しました。ただし、有機液肥の研究開発の当初、液肥製造装置内に存在する微生物が未解明であったため、液肥の安定的な維持管理法がわかりませんでした。
産総研とIAIは、静岡大学、静岡工技研、沼津工技セとの共同研究により、液肥製造装置内の菌叢の解明に取り組み、硝酸態窒素の産生に重要な微生物を特定しました。これにより、われわれはこの微生物の性質に合わせて、装置の運転条件を最適化することに成功しました(2021年3月30日 産総研プレス発表[3])。
しかし、製造した液肥の施肥効果の評価はできていませんでした。われわれは、市販の化学液肥と比較することで、微生物が作った有機液肥がトマトの水耕栽培に実用可能か、どのような施肥効果があるかなどを検証しました。
本開発は静岡県の「先端企業育成プロジェクト推進事業」(2016〜2018年度)による支援を受けています。
[1]https://www.aist.go.jp/aist_j/press_release/pr2019/pr20190513/pr20190513.html
[2]https://www.aist.go.jp/aist_j/press_release/pr2021/pr20210909/pr20210909.html
[3]https://www.aist.go.jp/aist_j/press_release/pr2021/pr20210330_2/pr20210330_2.html
研究の内容
われわれは、有機液肥と化学液肥を使い、それぞれ27株のトマトの水耕栽培を96日のあいだ行いました。栄養成分としての硝酸イオン濃度は、両液肥で同じとなるように調整されています。図1は、植物体の茎の太さを計測した結果です。有機液肥を使用した場合、化学液肥と比べて植物体が10%程度大きくなりました。また、トマト果実も化学液肥を使用した場合と同等量が収穫できました。
[画像2: https://prtimes.jp/i/113674/43/resize/d113674-43-08722a887d90aa43342e-1.png ]
化学液肥と比べて、有機液肥を使うとトマトの根に定着する微生物に違いが生ずるのかを菌叢解析によって調べました(図2A)。その結果、使用した有機液肥自体に複数の微生物が含まれ、それらのうちの3種(Rudaea属細菌、Stenotrophobacter属細菌、Chitinophaga属細菌)が比較的高い割合で根に定着していました(図2A中のそれぞれ赤・青・黄色で示した微生物)。顕微鏡解析を行ったところ、有機液肥で栽培したトマトの根には、化学液肥のそれと比較して多量のバイオフィルムが形成されていることがわかりました(図2B)。
検出された3種の微生物は、植物の成長を促進したり病原性微生物の感染を防いだりなど、植物の生育に有利な働きをする微生物と近縁でした。これらの微生物の働きによって、トマトの植物体が大きく生育した可能性が考えられます。この有機液肥を使用すると、トマトが感染性の疾病にかかりにくいことが、現場では経験的にわかっていました。今回の研究により、有機液肥に由来する微生物が根に定着してバイオフィルムを作り、根の表面を覆うことで、結果的に病原性を有する他の微生物の侵入を防いでいることが示唆されました。
[画像3: https://prtimes.jp/i/113674/43/resize/d113674-43-a4cd5f9aeeb0a13fa888-2.png ]
食品加工廃水を原料にして微生物の活性で作った有機液肥は、トマトの水耕栽培に有効であり、市販の化学液肥と比べても同等の施肥効果がありました。これらの技術や取り組みは、廃棄物を有効利用して資源循環を促進し、持続可能な社会の実現に役立ちます。
今後の予定
産総研は、本プロジェクト以外に、廃水から燃料となるメタンガスを生産するなど、微生物の力で廃棄物を有価物に変換する技術を開発しています。それら技術の効率や安定性を向上できるように、微生物の性質を理解して最大限に機能を活用する研究を進めています。
IAIは、水耕栽培を実用規模にするため、液肥製造装置を拡充・大型化しました。現在、水耕栽培の施設の大型化および高効率化も行い、液肥によるトマト水耕栽培についての事業化を進めています。
論文情報
掲載誌:Applied Microbiology and Biotechnology
論文タイトル:Microbially produced fertilizer provides rhizobacteria to hydroponic tomato roots by forming beneficial biofilms
著者:Yuya Sato, Teruhiko Miwa, Tomohiro Inaba, Takuto Akachi, Eiji Tanaka, Tomoyuki Hori, Keita Murofushi, Hiroshi Takagi, Hiroyuki Futamata, Tomo Aoyagi, Hiroshi Habe
DOI:https://doi.org/10.1007/s00253-023-12794-9
用語解説
有機液肥
植物の栄養成分である窒素・リン酸・カリウムを含む動植物性肥料および化学的処理を用いずに動植物性材料などの天然物質を原料に作成した肥料を有機肥料という。日本農林規格(JAS)によって定められる方法で製造され、認定を受けたものをいう。有機肥料のうち、液状のものを有機液肥という。
水耕栽培
土を使わず、水と液体肥料で野菜などの植物を栽培する方法。土耕栽培と比べて衛生管理や温度などの栽培条件の制御が簡単で、省スペースでも栽培ができることなどのメリットがある。
バイオフィルム
微生物の集団が形成する構造体の総称。風呂場や排水溝のぬめり、歯垢(しこう)などに代表される。一般にバイオフィルム状態の微生物は環境変化などに対する抵抗性が上がっているとされ、バイオフィルム内の微生物は安定的に保持されやすいと考えられる。
窒素資源循環
廃棄物に含まれる有価物や資源を取り出して再利用することなどにより、資源の喪失を抑えて循環させることを資源循環という。本稿では、窒素元素を資源として捉え、廃棄物などから窒素化合物を回収・再利用などすることで循環させることを窒素資源循環という。
次世代シークエンサー
従来に比べ、飛躍的に解析速度が向上したDNA塩基配列解読装置。1試料あたり数千から数万種もの微生物の同定が可能であり、100から200試料を同時並行で解析可能。
菌叢(きんそう)・菌叢解析
特定の環境中・生態系に存在する微生物の集合を菌叢という。菌叢の組成構造(どのような微生物がどれだけいるかという情報)の解析を菌叢解析という。細菌の代表的分子系統マーカー遺伝子である16S rRNA遺伝子を指標に、次世代シークエンサーを用いて行うことが主流。
硝酸態窒素・硝酸イオン
硝酸イオンは、化学式NO3-で表される酸化型の窒素化合物。硝酸態窒素は、硝酸イオンの状態の窒素をさす。自然界では、微生物の作用により、アンモニアが酸化されることで硝酸イオンが生じる。微生物により、アンモニアの酸化から硝酸イオンが生じる一連の反応を硝化といい、硝化作用を担う微生物を硝化細菌という。
・食品加工廃水を有機液肥に変換し農業利用
・市販の化学液肥と同等の効果
・微生物がバイオフィルムを形成してトマトの根を守る
[画像1: https://prtimes.jp/i/113674/43/resize/d113674-43-26df85b24ee11b7d990d-0.png ]
概 要
国立研究開発法人 産業技術総合研究所(以下「産総研」という)環境創生研究部門 佐藤 由也 主任研究員、稲葉 知大 主任研究員、羽部 浩 副研究部門長は、株式会社 アイエイアイ(以下「IAI」という)赤地 拓澄 研究員、静岡県工業技術研究所 (以下「静岡工技研」という)室伏 敬太 上席研究員、沼津工業技術支援センター(以下「沼津工技セ」という)高木 啓詞 主任研究員、静岡大学 二又 裕之 教授らと共同で、微生物による分解活性を利用して食品加工廃水から作った有機液肥が、トマト水耕栽培で実用可能なことを実証しました。
IAIは有機液肥の製造装置を開発し、産総研らと有機液肥の製造方法を確立しました。しかし、有機液肥の性能の評価はできていませんでした。製造した有機液肥と市販の化学液肥の性能比較のため、トマトの水耕栽培を行いました。一般的に、栄養成分量を自由に決められる化学肥料の方が、有機肥料よりも植物の成長効率が高いことが知られています。本研究で製造した有機液肥は、化学液肥と比較して、植物体を約10%大きく成長させ、市販の化学肥料と同等の施肥効果を示しました。この有機液肥は微生物を含んでいます。微生物の一部がトマトの根に定着してバイオフィルムを形成することで、他の微生物の感染を防ぐ可能性が示唆されました。本技術は、廃棄物由来の肥料を利用することで、窒素資源循環を促し、持続可能な社会の実現に貢献します。
この研究成果の詳細は、2023年9月29日(日本時間)に「Applied Microbiology and Biotechnology」誌に掲載されます。
下線部は【用語解説】参照
※本プレスリリースでは、化学式や単位記号の上付き・下付き文字を、通常の文字と同じ大きさで表記しております。
PR TIMESのシステムでは特殊文字は使用できないため、正式な表記とは異なることご留意ください。
正式な表記でご覧になりたい方は、産総研WEBページ(https://www.aist.go.jp/aist_j/press_release/pr2023/pr20230929/pr20230929.html)をご覧ください。
研究の社会的背景
持続可能な社会の実現には、革新的な資源循環技術の開発が必要です。IAIでは、微生物が有機物を分解することを利用して、食品加工廃水から有機液肥を製造する技術の開発に取り組んできました。
一般的に、化学肥料は、栄養成分の量を自由に調整できるため、食品残渣などを原料とした有機肥料と比べて植物の成長効率が高いことで知られています。IAIが製造した有機液肥は、トマトなどの水耕栽培に利用できます。しかし、市販の化学液肥と比較した場合の施肥効果の違いや特徴はわかっていませんでした。
研究の経緯
産総研は、次世代シークエンサーを用いた菌叢(きんそう)解析技術を用い、廃水処理装置や自然環境などを対象にさまざまな菌叢を解明し、有害物質の分解・除去に関わる微生物を特定してきました(2019年5月13日 産総研プレス発表[1]、2021年9月9日 産総研プレス発表[2])。
資源循環や環境負荷低減の観点から、IAIではタンパク質を多く含む魚の煮汁などの水産加工廃水を原料とし、微生物を用いて、窒素系の有機液肥の製造を可能にする装置を開発しました。ただし、有機液肥の研究開発の当初、液肥製造装置内に存在する微生物が未解明であったため、液肥の安定的な維持管理法がわかりませんでした。
産総研とIAIは、静岡大学、静岡工技研、沼津工技セとの共同研究により、液肥製造装置内の菌叢の解明に取り組み、硝酸態窒素の産生に重要な微生物を特定しました。これにより、われわれはこの微生物の性質に合わせて、装置の運転条件を最適化することに成功しました(2021年3月30日 産総研プレス発表[3])。
しかし、製造した液肥の施肥効果の評価はできていませんでした。われわれは、市販の化学液肥と比較することで、微生物が作った有機液肥がトマトの水耕栽培に実用可能か、どのような施肥効果があるかなどを検証しました。
本開発は静岡県の「先端企業育成プロジェクト推進事業」(2016〜2018年度)による支援を受けています。
[1]https://www.aist.go.jp/aist_j/press_release/pr2019/pr20190513/pr20190513.html
[2]https://www.aist.go.jp/aist_j/press_release/pr2021/pr20210909/pr20210909.html
[3]https://www.aist.go.jp/aist_j/press_release/pr2021/pr20210330_2/pr20210330_2.html
研究の内容
われわれは、有機液肥と化学液肥を使い、それぞれ27株のトマトの水耕栽培を96日のあいだ行いました。栄養成分としての硝酸イオン濃度は、両液肥で同じとなるように調整されています。図1は、植物体の茎の太さを計測した結果です。有機液肥を使用した場合、化学液肥と比べて植物体が10%程度大きくなりました。また、トマト果実も化学液肥を使用した場合と同等量が収穫できました。
[画像2: https://prtimes.jp/i/113674/43/resize/d113674-43-08722a887d90aa43342e-1.png ]
化学液肥と比べて、有機液肥を使うとトマトの根に定着する微生物に違いが生ずるのかを菌叢解析によって調べました(図2A)。その結果、使用した有機液肥自体に複数の微生物が含まれ、それらのうちの3種(Rudaea属細菌、Stenotrophobacter属細菌、Chitinophaga属細菌)が比較的高い割合で根に定着していました(図2A中のそれぞれ赤・青・黄色で示した微生物)。顕微鏡解析を行ったところ、有機液肥で栽培したトマトの根には、化学液肥のそれと比較して多量のバイオフィルムが形成されていることがわかりました(図2B)。
検出された3種の微生物は、植物の成長を促進したり病原性微生物の感染を防いだりなど、植物の生育に有利な働きをする微生物と近縁でした。これらの微生物の働きによって、トマトの植物体が大きく生育した可能性が考えられます。この有機液肥を使用すると、トマトが感染性の疾病にかかりにくいことが、現場では経験的にわかっていました。今回の研究により、有機液肥に由来する微生物が根に定着してバイオフィルムを作り、根の表面を覆うことで、結果的に病原性を有する他の微生物の侵入を防いでいることが示唆されました。
[画像3: https://prtimes.jp/i/113674/43/resize/d113674-43-a4cd5f9aeeb0a13fa888-2.png ]
食品加工廃水を原料にして微生物の活性で作った有機液肥は、トマトの水耕栽培に有効であり、市販の化学液肥と比べても同等の施肥効果がありました。これらの技術や取り組みは、廃棄物を有効利用して資源循環を促進し、持続可能な社会の実現に役立ちます。
今後の予定
産総研は、本プロジェクト以外に、廃水から燃料となるメタンガスを生産するなど、微生物の力で廃棄物を有価物に変換する技術を開発しています。それら技術の効率や安定性を向上できるように、微生物の性質を理解して最大限に機能を活用する研究を進めています。
IAIは、水耕栽培を実用規模にするため、液肥製造装置を拡充・大型化しました。現在、水耕栽培の施設の大型化および高効率化も行い、液肥によるトマト水耕栽培についての事業化を進めています。
論文情報
掲載誌:Applied Microbiology and Biotechnology
論文タイトル:Microbially produced fertilizer provides rhizobacteria to hydroponic tomato roots by forming beneficial biofilms
著者:Yuya Sato, Teruhiko Miwa, Tomohiro Inaba, Takuto Akachi, Eiji Tanaka, Tomoyuki Hori, Keita Murofushi, Hiroshi Takagi, Hiroyuki Futamata, Tomo Aoyagi, Hiroshi Habe
DOI:https://doi.org/10.1007/s00253-023-12794-9
用語解説
有機液肥
植物の栄養成分である窒素・リン酸・カリウムを含む動植物性肥料および化学的処理を用いずに動植物性材料などの天然物質を原料に作成した肥料を有機肥料という。日本農林規格(JAS)によって定められる方法で製造され、認定を受けたものをいう。有機肥料のうち、液状のものを有機液肥という。
水耕栽培
土を使わず、水と液体肥料で野菜などの植物を栽培する方法。土耕栽培と比べて衛生管理や温度などの栽培条件の制御が簡単で、省スペースでも栽培ができることなどのメリットがある。
バイオフィルム
微生物の集団が形成する構造体の総称。風呂場や排水溝のぬめり、歯垢(しこう)などに代表される。一般にバイオフィルム状態の微生物は環境変化などに対する抵抗性が上がっているとされ、バイオフィルム内の微生物は安定的に保持されやすいと考えられる。
窒素資源循環
廃棄物に含まれる有価物や資源を取り出して再利用することなどにより、資源の喪失を抑えて循環させることを資源循環という。本稿では、窒素元素を資源として捉え、廃棄物などから窒素化合物を回収・再利用などすることで循環させることを窒素資源循環という。
次世代シークエンサー
従来に比べ、飛躍的に解析速度が向上したDNA塩基配列解読装置。1試料あたり数千から数万種もの微生物の同定が可能であり、100から200試料を同時並行で解析可能。
菌叢(きんそう)・菌叢解析
特定の環境中・生態系に存在する微生物の集合を菌叢という。菌叢の組成構造(どのような微生物がどれだけいるかという情報)の解析を菌叢解析という。細菌の代表的分子系統マーカー遺伝子である16S rRNA遺伝子を指標に、次世代シークエンサーを用いて行うことが主流。
硝酸態窒素・硝酸イオン
硝酸イオンは、化学式NO3-で表される酸化型の窒素化合物。硝酸態窒素は、硝酸イオンの状態の窒素をさす。自然界では、微生物の作用により、アンモニアが酸化されることで硝酸イオンが生じる。微生物により、アンモニアの酸化から硝酸イオンが生じる一連の反応を硝化といい、硝化作用を担う微生物を硝化細菌という。
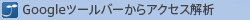

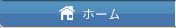
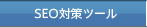
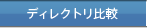

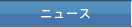



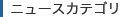
 SEO関連
SEO関連