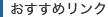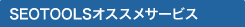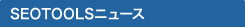スペースバリューHD Research Memo(5):戦略的M&Aを含めた事業領域の拡充が売上高の伸びをけん引
[21/02/01]
提供元:株式会社フィスコ
提供元:株式会社フィスコ
注目トピックス 日本株
■スペースバリューホールディングス<1448>の業績推移
過去8年間※の売上高推移を見ると、創業来の主力事業である「システム建築事業」、「立体駐車場事業」は総じて堅調に推移してきた。そのうえで、2014年3月期の伸びは、相鉄建設等の買収に伴う「総合建設事業」の拡大、2016年3月期は「開発事業」の本格展開、2017年3月期はコマツハウスの買収に伴う「システム建築事業」の拡大などによるものである。特に、2017年3月期は熊本地震への対応(応急仮設住宅の提供)に伴う一過性要因も重なり、過去最高を更新した。したがって、売上高の伸びをけん引してきたのは、相次ぐM&Aによる事業基盤の強化のほか、「開発事業」や「ファシリティマネジメント事業」への参入等を通じた事業領域の拡充によるところが大きい。ただ、ここ数年については、日成ビルド工業における会計不祥事案に端を発する内部体制の強化に専念してきたことなどから、売上高の伸びは頭打ちの状況が続いている。
※2018年3月期以前の業績は日成ビルド工業の業績となる。
利益面では、2017年3月期までの営業利益率はおよそ7%〜8%水準で推移し、売上高の拡大とともに増益基調をたどってきた(2017年3月期の親会社に帰属する当期純利益は過去最高を更新)。ただ、2018年3月期以降は、売上構成の変化や海外M&Aの影響(減価償却費やのれん償却費の増加)などが営業利益率の低下要因となっている。さらに2020年3月期は、会計不祥事の再発防止策遂行にかかる費用計上(一過性費用)も影響した。今後は、収益性の高い「システム建築事業」の伸びや事業間シナジーの創出により収益性の改善を図る方針である。
財政状態についても、総資産はM&Aや「開発事業」の展開などにより増加傾向をたどってきた。一方、自己資本も内部留保の積み増しや新株予約権の行使等により増加し、自己資本比率はおおむね30%台で推移しており、財務の安全性に懸念はない。なお、2020年3月期に総資産が減少に転じたのは、ホテル開発事業からの撤退方針を受け同事業にかかる資産の整理を進めたことによるものである。一方、資本効率を示すROEは2018年3月期まで10%以上を確保してきたものの、2019年3月期以降は利益率の低下に伴って低調に推移している。もっとも、2019年3月期のROEの落ち込みは一過性要因(開発資産の減損処理)によるところが大きい。今後は、利益率(収益性)の改善とともにROEの向上にも取り組む考えだ。
(執筆:フィスコ客員アナリスト 柴田郁夫)
<EY>
過去8年間※の売上高推移を見ると、創業来の主力事業である「システム建築事業」、「立体駐車場事業」は総じて堅調に推移してきた。そのうえで、2014年3月期の伸びは、相鉄建設等の買収に伴う「総合建設事業」の拡大、2016年3月期は「開発事業」の本格展開、2017年3月期はコマツハウスの買収に伴う「システム建築事業」の拡大などによるものである。特に、2017年3月期は熊本地震への対応(応急仮設住宅の提供)に伴う一過性要因も重なり、過去最高を更新した。したがって、売上高の伸びをけん引してきたのは、相次ぐM&Aによる事業基盤の強化のほか、「開発事業」や「ファシリティマネジメント事業」への参入等を通じた事業領域の拡充によるところが大きい。ただ、ここ数年については、日成ビルド工業における会計不祥事案に端を発する内部体制の強化に専念してきたことなどから、売上高の伸びは頭打ちの状況が続いている。
※2018年3月期以前の業績は日成ビルド工業の業績となる。
利益面では、2017年3月期までの営業利益率はおよそ7%〜8%水準で推移し、売上高の拡大とともに増益基調をたどってきた(2017年3月期の親会社に帰属する当期純利益は過去最高を更新)。ただ、2018年3月期以降は、売上構成の変化や海外M&Aの影響(減価償却費やのれん償却費の増加)などが営業利益率の低下要因となっている。さらに2020年3月期は、会計不祥事の再発防止策遂行にかかる費用計上(一過性費用)も影響した。今後は、収益性の高い「システム建築事業」の伸びや事業間シナジーの創出により収益性の改善を図る方針である。
財政状態についても、総資産はM&Aや「開発事業」の展開などにより増加傾向をたどってきた。一方、自己資本も内部留保の積み増しや新株予約権の行使等により増加し、自己資本比率はおおむね30%台で推移しており、財務の安全性に懸念はない。なお、2020年3月期に総資産が減少に転じたのは、ホテル開発事業からの撤退方針を受け同事業にかかる資産の整理を進めたことによるものである。一方、資本効率を示すROEは2018年3月期まで10%以上を確保してきたものの、2019年3月期以降は利益率の低下に伴って低調に推移している。もっとも、2019年3月期のROEの落ち込みは一過性要因(開発資産の減損処理)によるところが大きい。今後は、利益率(収益性)の改善とともにROEの向上にも取り組む考えだ。
(執筆:フィスコ客員アナリスト 柴田郁夫)
<EY>
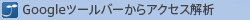

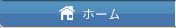
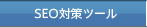
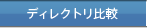

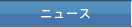




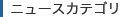
 SEO関連
SEO関連